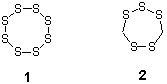
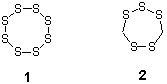
ところでイオウ単体は抗菌性をもっています。含硫化合物を含むアブラナ科植物などには、イオウそのものが成分としてはいっているものがあり、抗菌性を指標に成分検索をやったりしたときに有機溶媒可溶性の低極性成分として単離されることがあります。白色粉末がとれたのでマススペクトルをとってみると分子量256などというもっともらしいイオンが出るので、勇躍NMRを測定してみると、あれれ何にもピークが出ない、と頭を抱えることになります(笑)。
さて、varacin (3)のような1,2,3,4,5-ベンゾチエピン環もつ海洋天然物がいくつかあり、抗ガン性や抗菌性を示します。
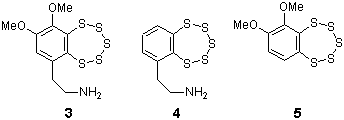
一見、なんでこんな構造のものが生理活性を示すのだろうと思いますね。イオウ分子の活性発現と何か関係があるのでしょうか。関連化合物の活性を調べてみると、3のメトキシ基を除去した化合物 (4)は高い細胞毒性を保持していますが、側鎖のアミノエチル基を除去した5では、活性が1/20以下に低下することがわかりました。
つまり、活性発現にアミノエチル側鎖が重要な役割を示していることになります。また、この末端アミノ基を三級アミンにすると活性が大きく低下することから、ここの窒素のローンペアによる求核性が反応の鍵であることが予想されます。
最近、明らかにされた反応経路は以下のようです。
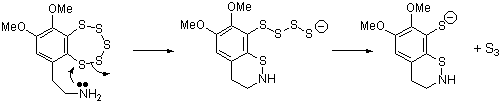
まず側鎖アミノ基がちょうど6員環を形成する位置のイオウ原子を求核攻撃して、その位置で環のS-S結合が開裂し、テトラスルフィドアニオンが生成します。そこから次いでS3分子が脱離して安定なフェニルチオラートアニオンになり、これがDNA切断などの生理活性発現の本体となります。側鎖アミノエチル基の欠けている分子ではこのような分子内活性化が起きないため、細胞毒性が低下しているわけですね。うまくできているものです。まさに自動発射装置をそなえた機能分子といっていいでしょう。
同様にしてイオウ分子S8もアミンなどの求核剤によって開環することが確かめられています。そのあたりにイオウの抗菌性の理由があるのかもしれません。
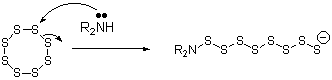
ref. E.M.Brzostowska and A.Greer J. Am. Chem. Soc., 2003, 125, 396-404.